古くから日本の食文化や民間療法に根付いてきた「よもぎ」。春の訪れを告げる草餅や、体を温めるよもぎ蒸しなど、その活用法は多岐にわたります。中でも「よもぎ茶」は、手軽にその恩恵を受けられる健康茶として、多くの人々に親しまれています。ノンカフェインで飲みやすく、リラックス効果や美容、健康維持に役立つとされることから、日常的に愛飲している方もいらっしゃるでしょう。
しかし、インターネット上などで「よもぎ茶は肝臓に悪い」という気になる噂を目にすることがあります。健康のために飲んでいるはずのお茶が、実は体に負担をかけているかもしれない…そう考えると不安になりますよね。「よもぎ茶 肝臓に悪い なぜ」そのような疑問を持つ方も少なくないでしょう。
この記事では、プロライターの視点から、なぜよもぎ茶が肝臓に悪いと言われることがあるのか、その真相に迫ります。
よもぎ茶とは?古来より伝わる万能ハーブの魅力
まず、「よもぎ茶が肝臓に悪い」という話の前に、よもぎ茶そのものについて理解を深めましょう。
よもぎ(蓬)は、キク科に属する多年草で、日本全国の道端や野原など、比較的身近な場所で自生しています。強い生命力を持ち、「ハーブの女王」とも呼ばれるほど、古くから薬草として重宝されてきました。
よもぎ茶は、主に春から夏にかけて採取したよもぎの葉を乾燥させ、場合によっては焙煎(ほうじ)して作られます。独特の爽やかな香りと、ほんのりとした苦味が特徴です。
含まれる主な成分と期待される効能:
よもぎ茶が健康茶として注目される理由は、その豊富な栄養成分にあります。
- クロロフィル(葉緑素): 緑色の色素成分で、「緑の血液」とも呼ばれます。血液をきれいにしたり、体内の不要な物質を排出するデトックス作用が期待されています。貧血予防にも役立つとされます。
- 食物繊維: 腸内環境を整え、便秘の解消をサポートします。腸が健康であることは、全身の健康、もちろん肝臓の負担軽減にも繋がります。
- ビタミン類: 特に血液凝固に関わるビタミンKが豊富です。その他、β-カロテン(体内でビタミンAに変換)、ビタミンCなども含みます。
- ミネラル類: カリウム、カルシウム、鉄分などが含まれています。特にカリウムは体内の余分なナトリウムを排出する働きがあり、むくみ解消や血圧調整に役立ちます。鉄分は貧血予防に重要です。
- 精油成分(シオネール、ツヨンなど): よもぎ特有の香りのもととなる成分です。シオネールにはリラックス効果や血行促進、利尿作用などが期待されます。一方、ツヨンは、後述する「肝臓に悪い」と言われる理由に関係する成分です。抗菌・抗炎症作用なども報告されています。
これらの成分により、よもぎ茶には一般的に以下のような効能が期待されています。
- 冷え性の改善: 血行促進作用により、体を温める効果が期待できます。
- 貧血予防: クロロフィルや鉄分の働きによります。
- 美肌効果: 抗酸化作用や血行促進、デトックス作用が肌の健康をサポートします。
- デトックス・便秘解消: 食物繊維やクロロフィルの働きによります。
- リラックス効果: 独特の香りが神経を落ち着かせると言われています。
- 生活習慣病予防: 抗酸化作用や血行促進などが関与すると考えられます。
このように、よもぎ茶は多くの魅力を持つ健康茶であることが分かります。では、なぜ「肝臓に悪い」という説が出てくるのでしょうか。
以下でもなぜよもぎ茶は肝臓に悪いと言われるのか解説していますか、自分自身で情報を入手していきましょう。
「よもぎ茶は肝臓に悪い」と言われるのはなぜ?その理由を徹底解説
多くの効能が期待されるよもぎ茶ですが、「肝臓に悪い」という噂が立つ背景には、いくつかの理由が考えられます。**「よもぎ茶 肝臓に悪い なぜ」**という疑問に、一つずつ答えていきましょう。
1. 精油成分「ツヨン(Thujone)」の存在
これが、「よもぎ茶が肝臓に悪い」と言われる最も大きな理由の一つと考えられます。
- ツヨンとは?: ツヨンは、よもぎやニガヨモギ、セージなどの特定の植物に含まれる天然の有機化合物(モノテルペンケトン類)です。独特の香りを持つ一方で、神経毒性や肝毒性を持つ可能性が指摘されています。
- 過去の事例(アブサン): かつてヨーロッパで人気を博した薬草系リキュール「アブサン」は、原料であるニガヨモギに含まれるツヨンが原因で、幻覚作用や中毒症状を引き起こすとされ、多くの国で製造・販売が禁止されました(現在はツヨン濃度を規制した上で製造が許可されている国もあります)。このアブサンのイメージが、同じくツヨンを含むよもぎにも影響を与えている可能性があります。
- 過剰摂取のリスク: 動物実験などでは、ツヨンを大量に投与した場合に、痙攣などの神経症状や、肝臓へのダメージが見られたという報告があります。肝臓は体内の化学物質を代謝・解毒する中心的な臓器であるため、特定の成分が過剰に摂取されると負担がかかる可能性があります。
- 日本の規制: 日本の食品衛生法では、ツヨン(具体的にはα-ツヨンとβ-ツヨンの合計)を含む可能性があるニガヨモギやセージについて、食品への使用に関する注意喚起や、特定の加工食品への使用制限などが設けられています。よもぎ自体が直接的に規制対象となっているわけではありませんが、ツヨンという成分に対する警戒感が、「よもぎ=危険」という短絡的なイメージに繋がっているのかもしれません。
ただし、重要な点があります。 通常、私たちがよもぎ茶として飲む場合、そのツヨンの含有量はごく微量であると考えられています。乾燥や焙煎といった加工工程で、揮発性の高いツヨンはある程度減少するとも言われています。アブサンのようにアルコールで成分を抽出したり、精油を直接摂取したりする場合とは異なり、お茶として適量を飲む範囲であれば、健康な人がツヨンによる深刻な健康被害を受ける可能性は極めて低いというのが一般的な見解です。
2. 肝臓への代謝負担の可能性
ハーブティー全般に言えることですが、植物に含まれる様々な成分は、体内で吸収された後、主に肝臓で代謝されます。特定の成分を、特に長期間にわたって大量に摂取し続けると、肝臓の代謝機能に負担がかかる可能性は否定できません。
よもぎ茶に含まれるどの成分が具体的にどれほどの負担になるかは一概には言えませんが、体質やその時の体調、他の食品や薬との組み合わせによっては、肝臓が処理しきれずに負担が増加することも考えられます。特に、既に肝機能が低下している方は、健康な人なら問題ない量の成分でも、代謝が追いつかず、肝臓にさらなるダメージを与えてしまうリスクがあります。
3. カリウムの含有量と腎機能への影響
よもぎにはカリウムが比較的多く含まれています。カリウムは体にとって必須のミネラルですが、腎臓の機能が低下している方が過剰に摂取すると、体外へうまく排泄されず、血液中のカリウム濃度が高くなる「高カリウム血症」を引き起こす可能性があります。高カリウム血症は、不整脈など心臓への悪影響を及ぼすことがあるため注意が必要です。
肝臓と腎臓は密接に関連しており、肝臓の病気が腎機能に影響を与えたり、その逆の場合もあります。そのため、腎機能に不安がある方は、カリウムを多く含むよもぎ茶の摂取にも慎重になる必要があります。これは直接的に「肝臓に悪い」というわけではありませんが、関連する注意点として挙げられます。
4. 情報の誤解や混同、個人の体験談の一般化
- 他のハーブとの混同: 健康茶やサプリメントの中には、実際に肝機能障害を引き起こした事例が報告されているものもあります。そうした情報とよもぎ茶の情報が混同され、「ハーブティーは肝臓に良くない」という大雑把な認識が広まっている可能性も考えられます。
- 個人の体験談: 特定の人がよもぎ茶を飲んで体調を崩した(アレルギー反応、元々の肝疾患の悪化など)という体験談が、「よもぎ茶は誰にとっても肝臓に悪い」かのように一般化されて伝わってしまうケースもあります。
これらの要因が複合的に絡み合い、「よもぎ茶は肝臓に悪い」という噂が形成されていると考えられます。しかし、繰り返しになりますが、健康な人が適量を守って飲む限りにおいては、過度に心配する必要はないというのが現在の一般的な考え方です。
よもぎ茶の安全性と適切な摂取量 ~安心して楽しむために~
では、よもぎ茶を安全に楽しむためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。適切な摂取量や、特に注意が必要な人について解説します。
一般的な安全性とツヨンの量について
前述の通り、食品として通常摂取されるよもぎ茶に含まれるツヨンの量は微量であり、健康リスクは低いと考えられています。欧州食品安全機関(EFSA)なども、食品からのツヨン摂取について評価を行っていますが、一般的な食生活における摂取量であれば、健康への懸念は低いとしています。
日本の食品安全委員会の資料などでも、よもぎを「適切に用いれば安全」あるいは「通常の食品に含まれる量ではおそらく安全」といった分類がされている場合が多いです。これは、極端な量を摂取しない限りは問題ないということを示唆しています。
適切な摂取量の目安は?
よもぎ茶の適量について、医学的に明確に「1日〇杯まで」と定められた基準はありません。製品によって濃度も異なるため、一概には言えませんが、一般的には1日に1~3杯程度を目安にするのが良いでしょう。
大切なのは以下の点です。
- 一度に大量に飲まない: ガブ飲みは避けましょう。
- 毎日過剰に飲み続けない: 特定のお茶だけを毎日大量に飲み続けるのではなく、他のお茶や水分とバランスよく摂取しましょう。
- 製品の指示に従う: 購入したよもぎ茶のパッケージに記載されている淹れ方や目安量を参考にしましょう。
- 自分の体調を観察する: 飲んでみて体調に変化がないか、不快な症状が出ないかなどを確認しながら、自分に合った量を見つけることが重要です。
「健康に良いから」といって、特定の食品や飲料だけを極端に摂取するのは、かえってバランスを崩す可能性があります。よもぎ茶も、あくまで健康維持のサポート役として、嗜好品の範囲で楽しむのが賢明です。
特に注意が必要な人
以下に該当する方は、よもぎ茶の飲用について、より慎重になるか、事前に医師や薬剤師に相談することをおすすめします。
- 肝臓疾患のある方: 肝機能が低下している場合、成分の代謝が負担になる可能性があります。自己判断せず、必ず主治医に相談してください。
- 腎臓疾患のある方: カリウム制限が必要な場合があります。医師に相談してください。
- キク科アレルギーのある方: よもぎはキク科の植物です。ブタクサやマリーゴールド、デイジーなどにアレルギーがある方は、交差反応を起こす可能性があります。
- 妊娠中・授乳中の女性: ツヨンには子宮収縮作用や神経系への影響の可能性が指摘されているため、妊娠中の摂取は避けるか、ごく少量にとどめるのが安全とされています。授乳中も、成分が母乳に移行する可能性を考慮し、控えるか医師に相談するのが望ましいでしょう。
- 特定の薬を服用中の方: よもぎ茶の成分が、服用中の薬の効果に影響を与える(相互作用)可能性があります。特に血液凝固阻止薬(ワルファリンなど、ビタミンKが影響するため)や、肝臓で代謝される薬などを服用している場合は、必ず医師や薬剤師にご相談ください。
- 乳幼児: 体が未発達な乳幼児への影響は不明な点が多いため、積極的な摂取は推奨されません。
よもぎ茶の選び方のポイント
- 信頼できるメーカーを選ぶ: 品質管理がしっかりしているメーカーの製品を選びましょう。
- 原材料を確認する: よもぎ100%か、他のハーブなどがブレンドされているかを確認しましょう。
- 可能であれば国産・無農薬を選ぶ: より安心して飲むことができます。
肝臓の健康を維持するために ~よもぎ茶は万能薬ではない~
「よもぎ茶が肝臓に悪い」という懸念について解説してきましたが、ここで強調したいのは、肝臓の健康は、特定のお茶を飲む・飲まないだけで決まるものではないということです。よもぎ茶は、あくまで健康的な生活習慣をサポートする一つの選択肢に過ぎません。
沈黙の臓器とも呼ばれる肝臓は、多少のダメージを受けても自覚症状が現れにくい臓器です。日頃から肝臓をいたわる生活を心がけることが何よりも大切です。
肝臓ケアのための生活習慣:
- バランスの取れた食事:
- 良質なタンパク質: 肝細胞の再生・修復に不可欠です(魚、大豆製品、赤身肉、卵など)。
- ビタミン・ミネラル: 肝臓の代謝機能をサポートします(野菜、果物、海藻類など)。特にビタミンB群、ビタミンC、ビタミンE、亜鉛、セレンなどが重要です。
- 食物繊維: 腸内環境を整え、有害物質の発生を抑えることで、肝臓への負担を間接的に軽減します。
- 避けるべきもの: 脂肪分の多い食事、糖質の過剰摂取、加工食品、インスタント食品は肝臓に負担をかけやすいので控えめに。
- アルコールの制限: アルコールの代謝は肝臓の大きな仕事です。過剰な飲酒は、脂肪肝、アルコール性肝炎、肝硬変のリスクを高めます。飲む場合は適量を守り、必ず休肝日を設けましょう。
- 適度な運動: ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、血行を促進し、代謝を高めます。また、肥満(特に内臓脂肪)は脂肪肝の原因となるため、運動による体重管理も重要です。
- 十分な睡眠と休養: 睡眠中に体は修復作業を行います。肝臓を休ませ、回復させるためにも、質の高い睡眠を十分にとることが大切です。
- ストレス管理: 過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血流を悪化させるなどして、間接的に肝臓機能にも影響を与える可能性があります。趣味やリラックスできる時間を取り入れ、上手にストレスを発散しましょう。
- 薬の適正使用: 薬も肝臓で代謝されるため、必要以上の薬やサプリメントの乱用は避けましょう。医師や薬剤師の指示に従って正しく使用することが大切です。
- 定期的な健康診断: 肝機能は血液検査(AST、ALT、γ-GTPなど)でチェックできます。自覚症状がなくても、定期的に健康診断を受け、自分の肝臓の状態を把握しておきましょう。
これらの基本的な生活習慣を整えることが、肝臓の健康を守るための最も確実な方法です。よもぎ茶は、こうした健康的な生活を送る上での、心地よい一杯として取り入れるのが良いでしょう。
まとめ:よもぎ茶と上手に付き合い、健やかな毎日を
今回は、「よもぎ茶が肝臓に悪いと言われるのはなぜ?」という疑問について、その背景にある理由と、安全な飲み方、そして肝臓ケアの基本について詳しく解説しました。
結論として、「よもぎ茶が肝臓に悪い」という説は、主にツヨンという成分の過剰摂取リスクや、体質・持病による肝臓への負担の可能性に基づいています。しかし、健康な人が常識的な範囲でよもぎ茶を飲む限りにおいては、そのリスクは非常に低いというのが一般的な見解です。よもぎ茶に含まれるクロロフィルや食物繊維、ビタミン、ミネラルなどの成分は、むしろ健康維持に役立つ可能性も秘めています。
**「よもぎ茶 肝臓に悪い なぜ」**と不安に感じていた方も、過剰摂取を避け、ご自身の体調をよく観察しながらであれば、よもぎ茶の持つ香りや風味、そして穏やかな効能を安心して楽しむことができるでしょう。
ただし、肝臓や腎臓に疾患のある方、妊娠・授乳中の方、キク科アレルギーの方、特定の薬を服用中の方は、必ず事前に医師や専門家に相談するようにしてください。
そして最も大切なことは、よもぎ茶を万能薬のように過信するのではなく、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な休養といった、日々の基本的な生活習慣を大切にすることです。これこそが、肝臓をはじめとする全身の健康を維持するための土台となります。
よもぎ茶は、私たちの生活に潤いと安らぎを与えてくれる素敵な飲み物の一つです。正しい知識を持ち、適量を守って、上手に日々の暮らしに取り入れていきましょう。この記事が、皆さまの健やかな毎日の一助となれば幸いです。

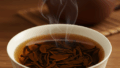
コメント